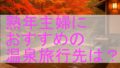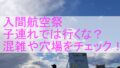「もしも知らない人に声をかけられたら?」
小学生の子どもを持つ親なら、
一度は考えたことがあるはず。
最近では不審者は日本人だけでなく、
たとえば学校の登下校時に
怪しい外国人が後ろをついてきたり。
一歩間違えれば誘拐につながる
事案もありますから本当に心配です!
ここでは、小学生低学年でもできる
“やさしい護身術”と、
毎日の生活でできる安全習慣、
そしておすすめの護身グッズを紹介します。
難しい技ではなく、
「逃げる」
「助けを呼ぶ」
「判断する」
力を育てる内容です。
親子で一緒に読みながら、
“自分を守る力”を身につけましょう。
子どもを守るために大切なこと|護身術を学ぶ前に知っておきたい基本
どうして子どもにも護身術が必要なの?
子どもに護身術なんて早いのでは?
と思う親御さんもいるかもしれません。
でも実は、小学生の低学年でも
「自分の身を守る力」
を少しずつ育てていくことは
とても大切なんです。
特に最近は、登下校や公園でのトラブル、
知らない人に声をかけられるケースも
ニュースでよく耳にします。
護身術は「戦う」ためではなく、
「逃げるため」
「助けを呼ぶため」
の力を育てるもの。
難しい技を覚えるのではなく、
自分の身に起きた危険を感じ取って、
素早く行動する
「判断力」と「行動力」
を身につけることが目的です。
親子で話しながら学ぶことで、
子どもも不安を抱えずに
前向きに取り組めます。
護身術とは、怖がるためのものではなく、
“自信を持って安全に生きる力”
を育てるための学びなのです。
「逃げる」がいちばんの護身って本当?
護身術の基本中の基本は
「逃げること」です。
相手がどんなに怖くても、
「戦おう」
と思わないことが一番大事。
大人でも、自分の安全を守るために
逃げる判断はとても大切です。
逃げることで大声を出し、
まわりに助けを求めるチャンスができます。
特に子どもの場合、力では
大人にかないません。
だからこそ、
「すぐ逃げる」
「大きな声を出す」
「近くの大人に知らせる」
という3つの行動を体で覚えておきましょう。
逃げる方向も大切です。
人が多い通りやお店、公園など、
助けを求めやすい場所を
普段から確認しておくと安心です。
護身術=戦うことではなく、
「逃げる勇気を持つこと」。
その考え方を親子で共有するだけで、
実際の危険への反応スピードが
大きく変わります。
不審者に会ったときの心の準備
不審者に出会ったとき、子どもはどうしても
驚いて固まってしまいがちです。
でも、「怖いときこそ動く」
という気持ちを事前に話しておくと、
実際の場面で大きな違いが出ます。
たとえば、
「知らない人に話しかけられたら?」
という場面を想定して、家で
ロールプレイするのがおすすめです。
「お母さんが迎えに来てるよ」
と言われたとき、
「本当?」
「どこにいるの?」
と聞かずに、
“信じないでその場を離れる”
ことを練習します。
また、怖いときは
「大声を出してもいい」
ということをしっかり
伝えてあげてください。
子どもは「怒られるかも」
と思って声を出せないこともあります。
安心して助けを呼べるよう、
家族で
「怖かったら全力で逃げていいんだよ」
と伝えることが何よりの備えです。
助けを呼ぶ声の出し方を練習しよう
大声を出すのは簡単そうに見えて、
実は練習が必要です。
特に子どもは緊張すると
声が出にくくなります。
だからこそ、普段から
「助けて!」
と叫ぶ練習をしておくのがポイントです。
公園や家の中で親子で遊びながら、
「どんな声が一番届くか?」
を試してみましょう。
「キャー」よりも「助けて!」や
「やめて!」など、はっきりした
言葉のほうが周囲に伝わりやすいです。
また、声の方向も大切。
相手に向かってではなく
、周囲の人に届くように
斜め上を向いて叫ぶと効果的です。
こうした練習を通じて、
いざというときに
「体が自然に動く」
ようになります。
護身術は「体の反射」
を育てることでもあり、
親子で笑いながら取り組むことで
楽しく身につけられます。
親子で話しておきたい「安全ルール」5つ
護身の第一歩は「ルールを共有すること」。
たとえば以下のような
5つのルールを決めておくと安心です。
安全ルール 内容
①知らない人についていかない
どんな理由でもついていかない
②助けて!を練習しておく
怖くなったら迷わず大声を出す
③通学路を確認しておく
危ない場所・助けを呼べる場所を把握
④連絡手段を持っておく
ブザーや防犯ベルなどを常備
⑤一人で遊ばない
なるべく友達と一緒に行動
このように、日常の中で
「安全ルール」
を話しておくことで、
子どもは「どうすればいいか」
を自然に理解できます。
護身術は特別なスキルではなく、
「毎日の中で少しずつ守る力を育てること」
なのです。
小学生でもできる!かんたんな護身術の基本動作
手をつかまれたときの抜け方
手をつかまれたとき、無理に力で引っ張っても
なかなか離れません。
大人と子どもでは力の差が大きいからです。
けれど、ちょっとしたコツを
知っていれば、小学生でも
簡単に逃げることができます。
まず覚えてほしいのは
「相手の指の間の方向に引く」こと。
相手が手首を握っているとき、
力がいちばん弱いのは
指と指の間の部分です。
そこに向かって素早く腕を引くと、
意外と簡単に抜けます。
このとき「いや!」や「やめて!」
と大きな声を出すことで、
周囲の人が気づきやすくなります。
親子で手をつないで
練習するのもおすすめ。
「こうつかまれたら、こう抜けるよ」
と遊び感覚で体に覚えさせましょう。
実際の場面で一瞬でも体が動けば、
逃げるチャンスは大きくなります。
大切なのは
「びっくりしても体が動く」
こと。
力よりも“タイミング”が
子どもの護身の鍵です。
背後から抱きつかれたらどうする?
後ろから抱きつかれると、
怖くて体が固まってしまいます。
でも、ここでも落ち着いて
「姿勢を低くして抜ける」
ことが大切です。
相手が後ろから腕を回してきたら、
前に体をかがめて小さくなり、
両腕を下にぐっと引き抜きましょう。
同時に大きな声を出して、
「助けて!」
と叫びながら足を動かすことも忘れずに。
このときのポイントは
“力で勝とうとしない”ことです。
背を低くして体の重心を下げると、
相手のバランスが崩れ、
すき間ができます。
そこを狙って腕を抜くのです。
護身術は「逃げるためのスキル」。
強さを競うものではありません。
お家で親子で背後から軽く抱く形を作って、
「こうやって体を前に倒して
逃げる練習しよう」
とやると楽しく身につきます。
怖い場面でも
「体が覚えている」ことが、
何よりの守りになります。
ランドセルを使った身の守り方
ランドセルは実は立派な防具になります。
たとえば、前に抱えて盾のように使えば、
相手の手を防ぐことができます。
特に低学年の子どもは、
手で押し返すよりもランドセルで
距離を取る方が安全です。
ランドセルを背負ったままでも、
相手に背中を見せずに
逃げる方向へ動くのがポイント。
もし前からつかまれそうになったら、
肩から外して胸の前に持ち、
間に挟んで「やめて!」
と叫びながら下がりましょう。
また、ランドセルのベルト部分は
つかまれやすい場所でもあります。
家で「つかまれたらどうする?」
という練習をしておくと安心です。
簡単に抜けるには、ベルトを
手で引っ張らず、体を小さく
回すようにして逃げると効果的です。
ランドセルは重たい荷物だけでなく、
子どもを守る
「小さな盾」
にもなるのです。
大声を出す・走る方向のポイント
逃げるときに大切なのは「声」と「方向」です。
まずは大きな声で助けを
呼びながら走ること。
叫ぶだけでも相手は驚き、
追いかけづらくなります。
走る方向は
「人が多いほう」
「明るいほう」
「お店があるほう」
を選ぶのが鉄則です。
たとえ遠回りでも、安全な道を
知っておくことが大切。
親子で登下校ルートを歩きながら、
「危険な場所」
「助けを呼べる場所」
に印をつけておくと、
実際に逃げるときに迷いません。
また、「走る=全力で逃げる」
練習もしておきましょう。
遊びの中で「助けてゲーム」
などをして、楽しく逃げる感覚を
覚えさせると、いざというときに
自然に体が動きます。
声と足、この2つの使い方を
知っているだけで、
護身力は大きく高まります。
毎日ちょっとずつ練習するコツ
護身術は一度覚えたら終わりではありません。
少しずつ繰り返すことで
「反射的に動ける力」
が育ちます。
たとえば、週に1回でも
「逃げる練習」
「声を出す練習」
を親子で行えば十分。
ポイントは“楽しく続けること”です。
ゲームのように
「逃げる」
「助けを呼ぶ」
「隠れる」
を組み合わせた遊びを取り入れると、
子どもも飽きずに続けられます。
また、日常の中で
「この道は危ないね」
「このお店に逃げられるね」
と話すことも立派な練習です。
護身術は体と心の両方を守る学び。
焦らず、少しずつ繰り返すことで、
子どもは自然と自信をつけていきます。
登下校や公園で気をつけたい危険シーンと対策
「声をかけられた」場面での安全な対応
知らない人に声をかけられたとき、
「返事をしてはいけない」
と教えるだけでは不十分です。
大切なのは
「どうやってその場から離れるか」
を練習しておくことです。
たとえば、「お母さんが呼んでるよ」
「かわいい犬がいるよ」
と言われたときは、
返事をせずに“すぐ離れる”が基本。
逃げるときには
「助けて!」ではなく
「知らない人がいます!」
と叫ぶと、周囲の大人が状況を理解しやすいです。
また、「近づかない距離」
も教えておきましょう。
3メートル(車1台分)以上離れて
話すのが安全な距離です。
親子でその距離を実際に歩いて
確認すると分かりやすいです。
声かけは日常で起こりうる危険なので、
「どう行動するか」
を体で覚えておくことが、
護身術の第一歩です。
車や人が少ない場所での危険サイン
静かな住宅街や裏道、公園のはしっこなど、
人通りが少ない場所は注意が必要です。
特に朝早い時間や夕方、
人が少なくなったときは危険が増します。
子どもには「静かすぎる道は避けよう」
と伝えましょう。
登下校ルートを親子で一緒に歩き、
「ここは車がよく通る」
「この道は暗くて見えにくい」
などを話すことが大切です。
また、知らない車がゆっくり
近づいてきたときは、止まらずに
方向を変えて逃げるのが安全です。
「不審者」だけでなく、
「環境」
そのものが危険になることもあります。
木が多くて見通しが悪い場所や、
遊具の裏など、死角になる場所は
一度確認しておきましょう。
子ども自身が
「ここはちょっと危ないかも」
と感じられるようになると、
自然と回避行動がとれるようになります。
友達と一緒にいるときの守り方
友達と一緒のときは油断しがちですが、
実はグループの中でも危険は起こります。
誰かが声をかけられても、
他の子が気づかないこともあるからです。
大切なのは、
「みんなで安全ルールを共有する」
こと。
たとえば
「知らない人が話しかけてきたら
全員でその場を離れる」
「1人がいなくなったら全員で大人に知らせる」
といったルールを決めておくと安心です。
また、友達同士で
「助けて!」
を聞いたらすぐ逃げることも教えましょう。
助けようとして一緒に
危険に巻き込まれることもあります。
安全の基本は
「みんなで逃げる」。
学校や地域で防犯教室がある場合は、
友達同士で参加するのもおすすめです。
夜や夕方の帰り道の工夫
夕方になると暗くなり、
人の顔や車のナンバーも見えにくくなります。
特に冬は16時台でも薄暗くなるため、
「早めに帰る」
「明るい道を通る」
を徹底しましょう。
反射材のついた服やカバン、
ライト付きのキーホルダー
などを使うと、自分の存在を
周囲に知らせやすくなります。
また、暗い場所ではスマホを見ながら
歩くのは絶対にNG。
注意力が落ち、危険に気づくのが遅れてしまいます。
「暗くなる前に帰る」
「人のいる道を歩く」
「寄り道しない」。
この3つを毎日の習慣にしておくと、
自然に身の安全を守れるようになります。
地域の大人やお店に助けを求める方法
逃げるときのゴールは
「安全な場所に行くこと」です。
そのために、近所の
「子ども110番の家」や
「助けを求められるお店」
を親子で確認しておきましょう。
商店街の中には
「防犯ステッカー」
を貼っている店も多く、
そこへ駆け込めば助けてもらえます。
「知らない人が怖かったです」
と伝えるだけで大丈夫。
お店の人は警察や家族に連絡してくれます。
また、地域の人との挨拶も大切です。
顔見知りが増えると、困ったときに
助けてもらいやすくなります。
日常の中で「助けてください」
と言える関係を作ることが、
最大の護身になります。
持っているだけで安心!子ども向け護身グッズ紹介
防犯ブザーの選び方と使い方
護身グッズの定番といえば防犯ブザー。
小学生には特におすすめです。
選ぶときは
「音量が大きい(85デシベル以上)」
「引きやすいストラップ」
「電池交換が簡単」
の3つがポイント。
子どもが自分で扱えることが何より大切です。
使う練習も忘れずに。
「引っ張るとこう鳴るよ」
と一緒に試し、どんな音が出るのか
確認しましょう。
怖がらず使えるようにしておくと、
いざというときすぐに使えます。
通学時はランドセルや
服の外側に付けるのが◎。
ブザーは「助けを呼ぶきっかけ」
になる大切な道具です。
何より、大声を出すのが難しい
私の子どものような内気な子でも、
ブザーを押すほうが簡単ですから。
内気なのは内気で困ったもん
なんですが(笑)
小学生でも使えるライト&反射グッズ
夜道では「自分の存在を見せる」ことが大事。
ライト付きのキーホルダーや
反射テープが便利です。
ライトはボタン一つで
光るタイプがおすすめ。
遊びながらでも安全に持てます。
反射材はランドセルや
靴に貼るだけでOK。
車のライトに反射して
ドライバーに気づいてもらえます。
「光る=守る」。
こうした意識を子どもに伝えることで、
安全意識が高まります。
かわいいキャラクター付きの
反射グッズも多いので、
楽しく安全を守りましょう。
かわいいけど強い!女の子向け防犯アイテム
女の子向けには、
「見た目がかわいいけど頼れる」
グッズが人気です。
たとえばハート型の防犯ブザーや、
アクセサリー風のライト付きキーホルダー。
かわいいデザインなら
毎日持ち歩くのも苦になりません。
また、小型スプレー
(催涙スプレーではなく香り付きミストタイプ)
を使うのもおすすめ。
危険時に相手の目をくらませるほど
強くなくても、
「びっくりさせて逃げる」
には十分です。
見た目と機能の両方を大切にしながら、
子どもが自分から
「持ちたい!」
と思えるデザインを選ぶことがポイントです。
男の子に人気の実用系グッズ
男の子には“ヒーローっぽい”護身グッズが人気。
LEDライト付きホイッスルや、
防水タイプの防犯ベルなどがあります。
「いざというときに使える!」
と感じることで、
持つことが誇りになります。
親子で
「どんなときに使う?」
「どうやって逃げる?」
を話しておくと、
使う場面をイメージしやすくなります。
護身グッズは“お守り”
ではなく“使うための道具”。
日常で持ち方や使い方を
確認しておくことが、
最大の備えになります。
持ち歩くときの注意点とルール
防犯グッズは
「持っているだけ」
では意味がありません。
使う場所、タイミングを知ることが大切です。
また、学校によっては
「防犯ブザー以外は禁止」
という場合もあるので、
ルールを確認してから持たせましょう。
使い方の練習も定期的に行い、
「壊れていないか」
「音が出るか」
をチェックするのを習慣に。
月に1度の点検で安全が続きます。
護身グッズは“安心の味方”。
正しく使えば、子どもの命を
守る大きな力になります。
親子でできる安全習慣|日常の中で身につける護身力
朝の見送り時にできる確認ポイント
毎朝の「いってらっしゃい」
は安全確認のチャンスです。
「防犯ブザー持った?」
「ルートは覚えてる?」
などの声かけを習慣にしましょう。
また、天気や時間によって
ルートを変えることも大切。
雨の日や冬の暗い時間帯は、
明るい道を選ぶように話し合いましょう。
短い時間でも毎日声をかけることで、
子どもは
「安全を意識して行動する」
習慣がつきます。
おうちでできる「もしもごっこ」練習法
ゲーム感覚で
「もしもごっこ」
をすると、護身の動きが楽しく身につきます。
たとえば、
「知らない人に声をかけられたらどうする?」
「背中をつかまれたら?」
といった場面を親が演じ、
子どもが答える形式です。
笑いながら練習しても、
体と頭はしっかり覚えます。
定期的に行うことで、いざというときに
自然に行動できるようになります。
SNSや動画での情報の扱い方
最近は、小学校低学年でも動画アプリや
SNSを使う子が増えています。
でも、そこにも危険があります。
顔や学校名を出すことで、
個人が特定されるケースも。
子どもには
「知らない人に個人情報を見せない」
「会話しない」
「写真を載せない」
などを教えましょう。
インターネットも
護身の対象のひとつです。
「見せる」「話す」
にも注意することが、
現代の新しい護身力です。
安全な道・危険な道を一緒にチェック
休日などに親子で通学路を歩き、
「ここが暗い」
「ここは逃げやすい」
と一緒に確認しておきましょう。
地図に印をつけると、子ども自身が
「ここに逃げよう」
と覚えやすくなります。
また、交番や
「子ども110番の家」
の位置も地図に書き込むと安心。
目で見る・歩いて覚えることで、
行動の速さがまったく違ってきます。
子どもが自信を持てる「安心の習慣」作り
護身術の最終的な目的は、
「怖がらずに自分を守る自信を育てること」です。
日々の挨拶、地域とのつながり、
親の見守りが子どもの心の支えになります。
「守られている」という安心感が、
勇気を生みます。
護身術は「逃げ方」だけではなく、
「信頼の積み重ね」。
それが子どもの安全の土台です。
まとめ
護身術は特別な力ではなく、
日常の中で身につけるべき、
小さな習慣の積み重ねです。
特に昨今は外国人も増えて、
治安の悪化が心配ですからね。
熊が増えている?
それもそうなんですが、
それはまた別の話。。
逃げ方を覚える、声を出す練習をする、
防犯グッズを使う、地域とつながる。
どれも「自分を守る力」
を育てる大切なステップです。
親子で笑顔で学びながら、
子どもが自信を持って生きていける
安全な環境を作っていきましょう。